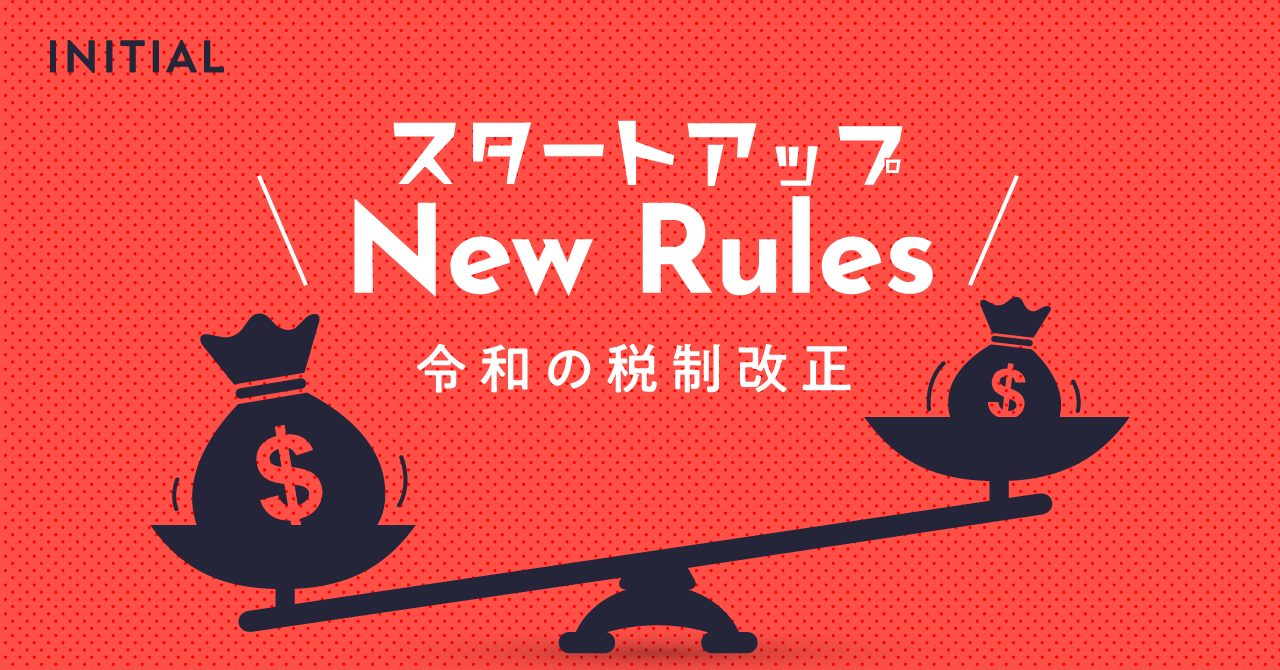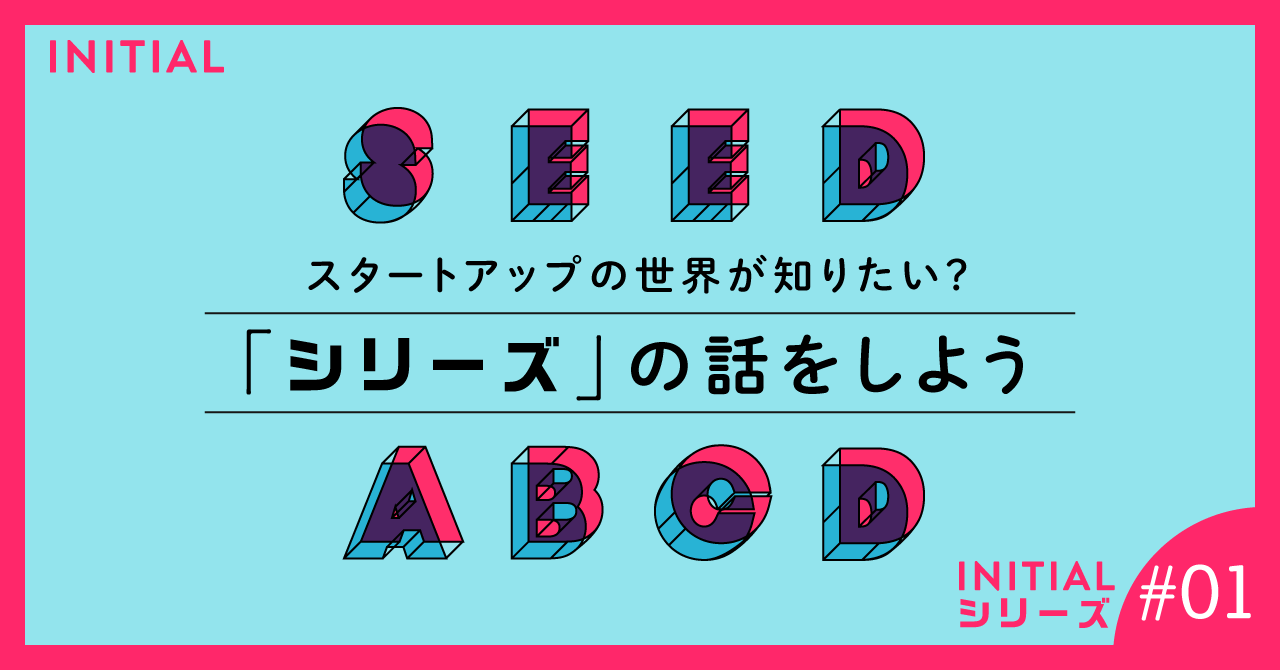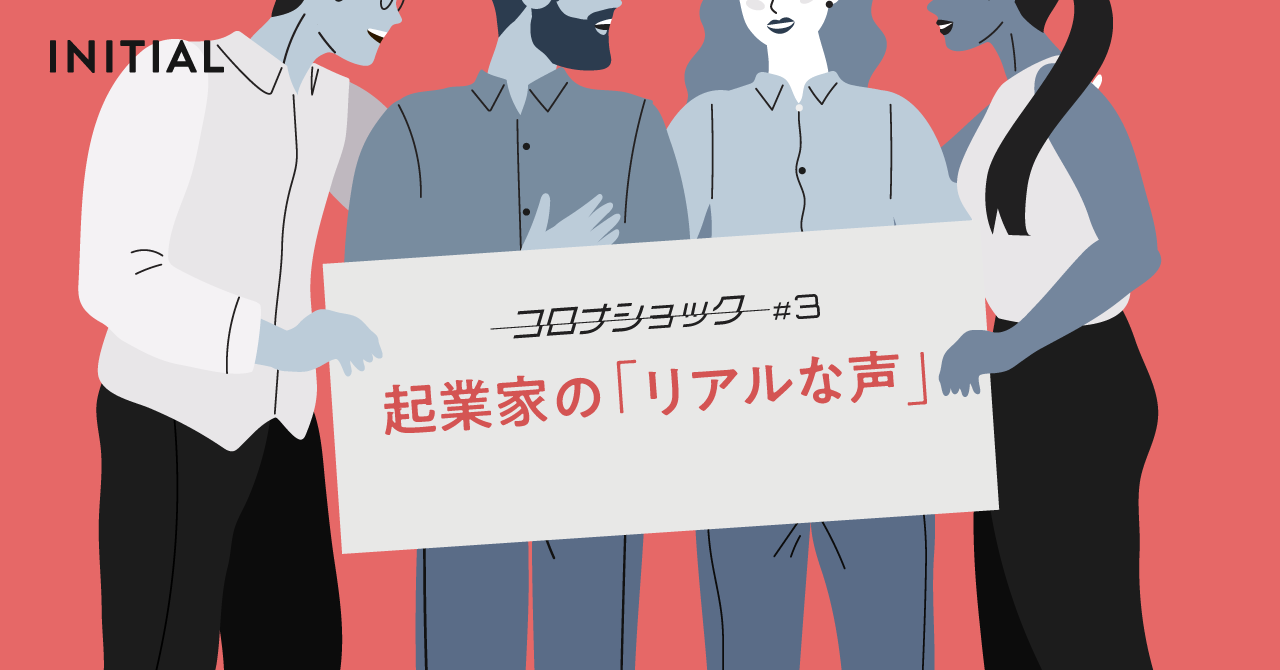2019年12月に「令和2年度税制改正大綱」が閣議決定され、その中でも「オープンイノベーション促進税制」は、大企業からスタートアップへの資金供給を促進する施策の1つとして期待されている。
2020年4月から開始が見込まれる本税制について、適用要件や対象となるスタートアップの特徴をおさらいし、日本のスタートアップ投資環境への影響を見る。
オープンイノベーション促進税制の概要
オープンイノベーション促進税制の概要は次の通りだ。

この税制がスタートアップの投資にどのような影響を与えるか、3つのポイントについて数値を基に確認していこう。
ポイント① 「事業会社とCVCに限定」
「経済産業関係 税制改正について」の中で経済産業省は、日本のスタートアップと事業会社によるオープンイノベーションの実施率の低さ、事業会社によるスタートアップ投資額の低さに課題感を示したうえで、「事業会社による単なる「お試し」では無いベンチャー企業の成長への本気の貢献を促す」と述べている。
実際に、これまで事業法人による1億円以上の投資はどの程度行われてきたのか。
2018年のスタートアップへの投資数は全3,944件あり、1億円以上の投資数は1,472件、その内事業法人による投資数は372件で全体の約9.4%であった。

また、2018年における事業会社及びCVCの投資先1社あたりの投資額中央値は、共に5,000万円であった。2009年から変動が少なく、1億円とは差が開いている。

事業法人による投資額の水準を1億円以上に引き上げ、スタートアップとの協業・提携を促すことが税制の狙いであり、適用対象が事業法人・CVCに限定されている背景である。
一方で、要件の中にオープンイノベーションの実施を義務付けるものは含まれていない。「1億円」と設定したハードルがオープンイノベーションの促進にどれだけ効果をもたらすかは、大企業の姿勢に左右される。
ポイント② 「設立後10年未満」のスタートアップ
設立後10年未満のスタートアップは、具体的にどう定義されているのか。
税制では「スタートアップ」の定義を、「新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を図る事業者」としている。
事業者は経済産業省に対し、1年間の出資案件に関して、「各出資が事業会社、スタートアップ双方の事業革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を決算期にまとめて報告する必要があり、このタイミングで税制適用されるかが判断される。
INITIALではスタートアップを「ユニークなテクノロジーや製品・サービス、ビジネスモデルをもち、事業成長のための投資を行い、事業成長拡大に取り組んでいる企業」「これまでの世界を覆し、新たな世界への変革にチャレンジする企業」と定義している。
それに従うとスタートアップ数(IPO企業を除く)は、2020/2/13現在で13,130社、その内設立が10年未満のものは6,981社。スタートアップの過半数、約53%が対象となる。
「設立後10年未満」と設定されているのは、会社自体は存続しているものの事業成長が鈍化してしまった、いわゆるリビングデッド化したスタートアップを対象から外す狙いがあると考えられる。
ポイント③ 「1億円以上の投資」に対する控除のインパクト
所得額が1億円、資本金が1億円以上の事業会社が、スタートアップに1億円を出資するケースを想定すると、次のように試算できる。

1億円をスタートアップに出資した場合、740万円の減税額となる。企業によって税率は多少変動することに注意が必要だが、出資金額の7.4%程度の減税効果が見込まれる。
次に実際に2019年に行われた資金調達の内、税制の要件と合致するケースを確認してみよう。

例えばヤマハ発動機は昨年6月、自動運転ソフトウェアを開発するティアフォーに対して18億円の投資を行っているが、仮にオープンイノベーション促進税制が適用されていた場合、1.3億円程度の所得控除が得られたと試算できる。
1件当たりの控除額上限は25億円のため、25%の所得控除が適用される1件当たりの投資額は最大で100億円。
2019年における最大の資金調達額は約100億円(スマートニュース)であったことを踏まえると、ほとんどの投資案件がカバーされる、踏み込んだ内容といえるだろう。
なお、年間の所得控除上限額は125億円とされており、年間適用投資額は最大で合計500億円となる。
税制がスタートアップに与える影響
控除要件の中に「投資額1億円」のハードルが設定されていること、半数以上のスタートアップが対象となること、一定の減税効果が得られることの3点を踏まえると、事業法人による投資額の中央値の底上げにつながる施策と考えられる。
また今回の税制は、楽天やサイバーエージェント等のIT企業で構成される、新経済連盟が作成した「2020年度税制改正に関する提言」の内容も踏まえ制定されたものと想定される。
スタートアップへの投資環境が、産業界の働きかけを契機に整備されたことは注目に値するポイントだ。
一方で懸念点もある。2020年2月7日時点で日本のユニコーン企業は7社存在しているが、東証全体で1,000億円を超える企業は800社程度。
ユニコーン企業は上場企業全体の上位25%に匹敵する推定評価額と考えると、既に東証1部の企業に見劣りしない規模だ。
評価額が上位のスタートアップは、株主が事業法人主体の企業も目立つ。
事業法人は事業シナジーを求める傾向があり、仮に「減税・オープンイノベーション」の思惑が優先されて投資が行われれば、正常なデューデリジェンスが働かずバリュエーションの高騰に繋がる恐れもある。
その結果、次の資金が必要なタイミングで出資も融資も受けられず、運営に行き詰るスタートアップが生まれる可能性もあるだろう。
また、相対的に立場の弱いスタートアップ側が大企業からの出資を断り切れず、大企業側のいわゆる派閥の影響をうけ、成長が制限されるなどの懸念も考えられよう。
しかし、スタートアップの成長を促す目的での資金供給、大企業側からみれば将来の事業へ投資を促すために踏み込んだ制度とみれる。
本制度を機に、より双方が歩み寄り、日本のイノベーション創出に繋がることを願う。
(執筆:三浦英之、編集:INITIAL編集部、デザイン:廣田奈緒美)