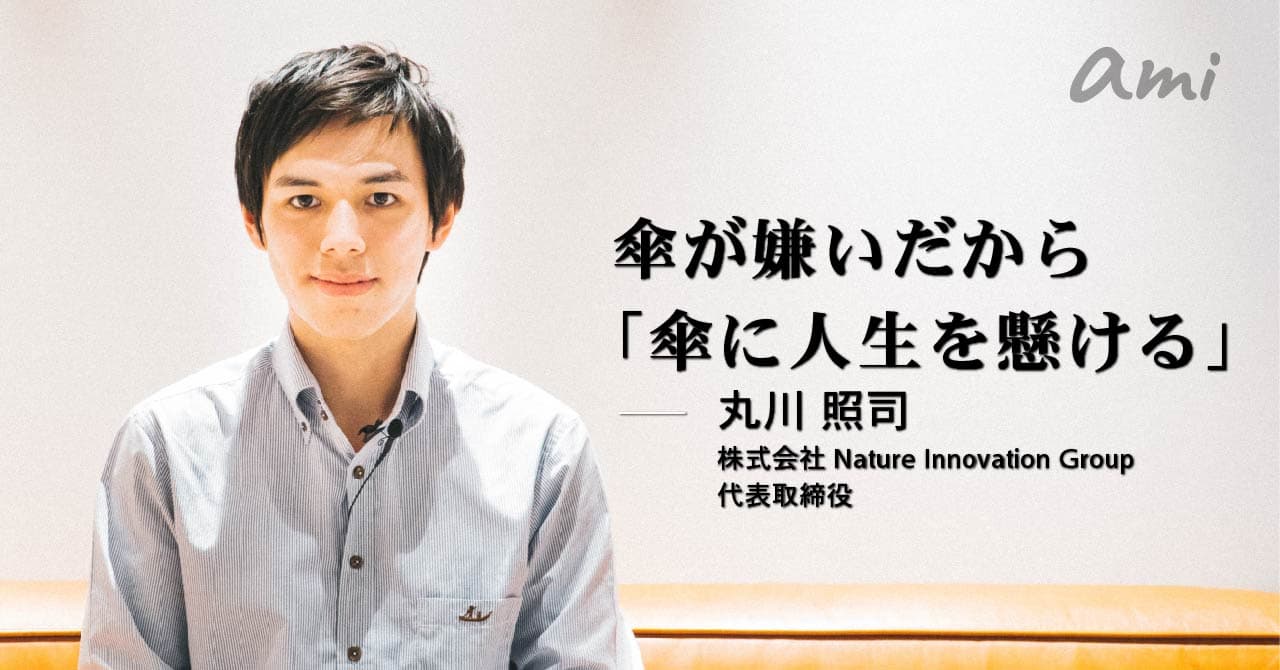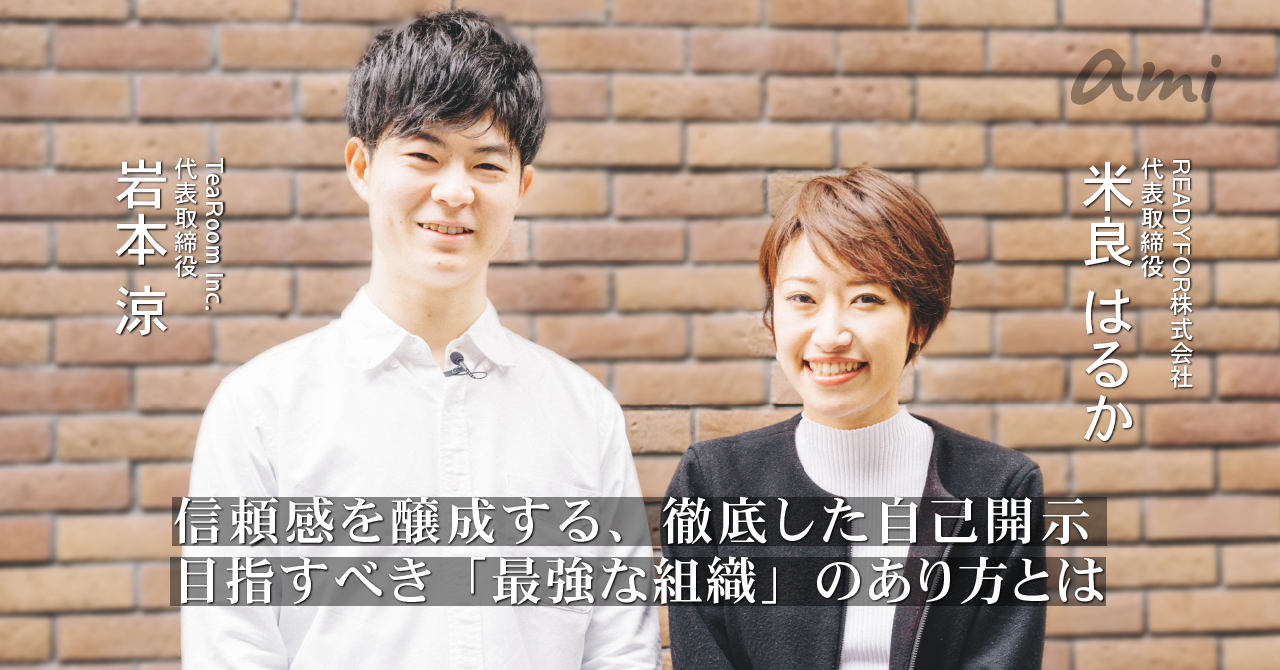
組織作りには、人、モノ、カネなど、いろいろな要素が複雑に絡み合っている。その複雑さを解決するための方法論も、多く世の中には出回っている。しかし、本当にその方法論は「本質」を捉えているのだろうか。
一度、組織を離れたからこそ分かった組織づくりの「本質」は、想像以上にシンプルだった。
「それ、寄付なの?」からのスタート
Readyforの事業についてお話いただいてもよろしいでしょうか。
Readyfor 米良さん(以下、米良) Readyforは2011年に日本で初めて、クラウドファンディングのサービスをスタートさせ、2014年にその事業を法人化しました。サービスを始めてからもうすぐ8年になります。
最初は誰も「クラウドファンディング」というキーワードを聞いたことがない状況から、今は多くの方がクラウドファンディングで資金調達をしてチャレンジをされるような状況になってきたので、いままで頑張ってきてよかったと思います。
日本で初めてクラウドファンディングというサービスをスタートしたので、最初はどういう仕組みなのかをユーザーの方に分かってもらえず、「それ、寄付なの?」といったことをずっと言われてきました。
しかしいまは、何かチャレンジする際に、「クラウドファンディングを使ってみたらどう?」と多くの人に言ってもらえるようになってきたので嬉しいですね。

米良さんの事業構想の中ではいまの状況はまだスタート地点という感じですか。
米良 そうですね。ようやくスタート地点に立った感じです。
クラウドファンディングは、資本主義の中で新しいお金の流れを生むかたちになりましたよね。
米良 そうですね。Readyforでは、今までの資本主義の中ではお金が流れにくいような「長期的にみたときに成果をあげる領域」であったり、「国などが補助金や助成金で援助をして成り立つ領域」に対して、民間の方々が少しずつお金を出し合って成り立たせるという思想をもっています。
なのでReadyforでは、とくにソーシャルセクターのNPOさんや病院、自治体、地方創生といったジャンルのチャレンジを今まで1万件ほど応援してきました。
社会的な意味はあるけれど、お金が流れない領域をカバーするためのクラウドファンディングをメインにされているということですね。
米良 世界中でいろんな思想のクラウドファンディングがあります。それこそモノづくりをやってみたい方を支援するものと、私たちのように今までお金が流れなかった領域にお金が流れるようにするものとでは、仕組みが大きく異なっていると思います。

私たちの場合は、「お金が流れにくい領域の人たちにお金を届けて、起業家やチャレンジャーを増やしていきたい」という想いが大きいので、その領域で今後もしっかりサービスを拡大していきたいと思っています。
昨今クラウドファンディングといっても、いろいろな領域にフォーカスしたものがありますが、Readyforさんはソーシャル的な意味合いが強い、「ユーザーの共感」を重視したプロジェクトが多いように感じます。プロジェクトに対して「共感されるか?」という要素を重要視しているのでしょうか。
米良 そうですね。先ほど説明したような「お金が流れにくい領域を支援する」という思想で事業を展開しているので、「ものが欲しいからお金を出す」といったEコマース的なクラウドファンディングの仕組みではなく、チャレンジャーの人が自分の夢や想いを伝えて、それに対して応援者を集めるような仕組みにしています。
なので「共感をさせる」ことは、Readyforではとても重要な要素だと思います。
Readyforというサービスのキーワードは「共感」ということですね。
共感を呼ぶコツは「抽象化せず具体化する」
共感に着目した、米良さんの原体験やきっかけは何だったのしょうか。
米良 共感に直結するか分かりませんが、大学生のときにパラリンピックのスキーチームの監督を支援するために、インターネットを使って寄付を募るプロジェクトを立ち上げて成功させた経験がReadyforを始めたきっかけになっています。

そのチームは、パラリンピックで何度も優勝しているすごいチームでしたが、マイナー競技であるがゆえの知名度の低さが原因で、しっかりした練習をできる環境が十分に整っていませんでした。
ただ、そんなマイナーな競技でも、パラリンピックのシーズンの瞬間はみんながすごく熱狂するんですよね。
その一次的な熱狂を活用してみんなが少しずつお金を出し合えば、日本を代表するチャレンジャーに対してお金を集めたり、日本人として誇りを持って応援できるんじゃないかと思っていました。
スキーのプロジェクトを始めた当時から、「共感や応援にお金を流すという領域は顕在化していないマーケットだが、インターネットテクノロジーを活用すれば事業として成立させることができるのでは」という仮説を持っていました。
人の気持ちが動きやすいプロジェクトの共通点は、どういうものでしょうか。
米良 プロジェクトのお手伝いをさせていただくときに、「このプロジェクトはどんな人に応援されたいですか?」ということをよく問わせていただきます。
社会性の高いプロジェクトでは、「平和をつくりたいから」といった自分の想いを前面に伝えがちですが、多くの人たちにとってその人を応援する理由は「なぜあなたがやるのか?」「なぜあなたができるのか?」という部分だと思います。
なので、「あなただったらできること」「あなただからこそできること」を明確にし、挑戦者の方にとって本当に応援をされたい人たちにプロジェクトがきちんと届くように、挑戦者とReadyforで協力してプロジェクトをつくるように心がけています。

大きなテーマを漠然と見せるのではなく、「応援する方にとって、いかに分かりやすく、自分事化しやすい伝え方になっているか」が、共感されるための重要な要素ということですね。
米良 そうですね。大きな夢だったり、大きな世界をつくりたいという気持ちはとても大切ですが、「その夢を実現させるための最初の一歩を誰に届けたいのか」を意識してプロジェクトをつくると多くの人に刺さりますし、その結果周りにも波及し、予想していなかった人たちも応援してくれるようになると思うので、「抽象化せず具体化する」ことが大切だと思います。
人生100年時代に大切なこと
今までご覧になってきた中で、とくに思い入れのあるプロジェクトはどういうものがあるのでしょうか。
米良 限界集落に住んでいる70歳ぐらいの方が立ち上げた、「どうしても限界集落でコミュニティレストランを作りたい」というプロジェクトは印象に残っています。
その方はすでに仕事を引退されていたので、クレジットがないということで銀行は資金を貸してくれませんでした。ただ、自分の資産を担保に入れてお金を借りるというのはその方自身も難しいと考えていらっしゃいました。
そんなときに、Readyforを見つけてくださってプロジェクトを立ち上げました。

その結果無事に100万円近くの支援が集まり、住人が30人ほどの集落にコミュニティレストランができました。その結果、週に1、2人ぐらい新しい人がその集落に遊びに来てくれるようになったんですね。
「1、2人」と東京の方が聞くと、「少なくないか?」と感じますが、プロジェクトの支援でお金を出した方に加え、「お金は出していないけど、こういう取り組みはすごく面白いと思って遊びにきました」という人が、30人しか住んでいない場所にどんどん集まってくるようになったそうです。
しかもその方は、引退するまではサラリーマンをされていましたが、そのプロジェクトがきっかけで大学などで講義をするようになったとおっしゃっていました。
今まで65歳が定年だった時代から、人生100年時代になってきている中で、そういった自分がやりたいチャレンジを何歳でも、どんな人でもできる世の中をつくりたいですし、そういうプロジェクトを応援していきたいと思っています。
自分が心からやりたいことを実現するための手段として、Readyforが見られるようになってきたということですよね。
米良 そうですね。
今の資本主義の社会では、まだまだお金を必要としているところにお金が行き届いていないなと思っています。
とくにリスクマネーと言われるような、チャレンジャーに対しての資金供給はすごく少ないと思っているので、そういった領域に対してもっとお金が届くような社会にしていきたいですね。
そして、社会、世界が持続的に成長していけるような新しいお金の流れを、Readyforを中心につくっていきたいなと思っています。
ありがとうございました。 続いて、もう1名のゲストとしてTeaRoomの岩本さんをお呼びしています。 まず岩本さんがどのような事業をされているかお話いただいてもよろしいでしょうか。
日本文化は「お茶」から学べる

TeaRoom 岩本(以下、岩本)よろしくお願いします。
われわれはTeaRoomという会社で、日本の文化や思想をいろいろな空間にインストールする事業をしておりまして、オフィス向けにお茶などの飲食分野や茶室を提供しています。
僕自身が茶人ということもあり、能動的に目にしたり、見聞きしないと日本文化を学べない現状を改善したいと感じています。
なので、ヨーロッパの美術館や街並みのアート性のように、自動的に日本文化を学べる環境をつくりたいという想いからオフィス向けのお茶プロダクトを提供しています。
今回質問させて頂きたいことは、全部で3つあります。
1つ目は、どうやって社内にビジョンを浸透させるのかについて。 そして2つ目はすぐにアクションを取れる組織を作る方法についてです。
以前米良さんが「昨日考えたことは今日やりたい、すぐやりたい」といったご発言をされていましたが、多くの場合社長がやりたいと言っても、すぐに組織が反応できないことが多いんじゃないかと思っています。
反応速度が速い組織をつくるために、どういった実務的な仕組みや連絡ツールを使っているかを教えていただきたいです。
3つ目は、周りの巻き込み方についてです。
今度、静岡の限界集落のような場所に弊社で工場を持つことになったのですが、そこにいらっしゃるおじいちゃんやおばあちゃんを巻き込んで、コミュニティ化しながら工場を運営していくためにはどうしたらいいかアドバイスを頂きたいです。
会社はメンバーの想いと強みでできていく

米良まず社内にビジョンを浸透させる方法について、お話しさせて頂きます。
自分もそうなのですが、起業家は自分で何でもやりたがる傾向が強いじゃないですか。なので、自分が見えている景色や考えを分かってくれるチームをつくりたがっていた時期が私にもありました。
ところが、一昨年の夏ぐらいにけっこう大きい病気をしてしまい、それまで6年間ほど、サービスをつくって、自分が社長になって、メンバーと一緒に歩んできた会社を7カ月ほど休むことになりました。
会社と自分の人生が同化するくらい会社が好きでしたし、自分の子どものように大切に思っていたので、会社を休むことが決まったとき、自分のアイデンティティが失われたように感じるほど悲しかったですね。
その後、ずっと一緒にやってきたCOOとCFOにその状況を伝えると、「全然大丈夫ですよ」「僕らが会社は守っていくから」というふうに言ってくれて。
悲しい気持ちがあった一方で、自分が生んだものをこんなにも愛をもって守ると言ってくれている人たちが近くにいたことを、改めて感じることができました。
なので、彼らに会社を預けて、自分が元気になって戻ってきたときにReadyforをどう成長させるかをしっかり考える療養の期間にしようと決めました。
休んでいる期間、会社のメンバーがお見舞いに来てくれていましたが、会社のことに自分は一切口を出さないと決めて、1回も私自身は仕事について触れずに経営業務を全部社員に任せました。
そのとき、会社の成長は自分だけじゃなく、メンバーみんなの想いと強みでできていくんだと改めて思いました。
私が休んでいる間も業績はすごい伸びていて、私いらないじゃんみたいな感じでしたが。(笑)
チームを作るのに重要なことは3つだけ

米良 そういった経験を通して、自分がやっぱりこの会社のなかで果たすべき役割を改めて実感しましたし、社員も私がいない組織を初めて経験して、私という人間がどういう価値を会社の中で出しているかを分かってくれたと思います。
なので、会社に戻ってから、「肩書とかを抜きにして、自分が苦手なことや嫌なことをできるだけやらずに、1人1人が強みを発揮できるようなチームをつくろう」とみんなで話し合いました。
自分の見えていないことが社内でどんどん走ると怖くなりますが、合宿を頻繁に行ったり経営陣でも密度濃く話すと、お互いを信頼をし合えるようになり、見えないという恐怖はなくなるんですよね。
社員1人1人に意思決定を任せるには、信頼は本当に大事だと思っているので、「信頼感を醸成する方法」は徹底的に考えています。
あとは、ビジョンも大事です。Readyforという会社が存在する理由は、「自分1人ではできないけど、自分が絶対叶えたいと思っているビジョンを叶えるため」だと思っています。
なので採用の際も、「1人じゃできないことも、この仲間とだったらできるるかもしれない」と入社後に思ってもらうためにも、徹底的にビジョンへの共感を見定めています。
Readyforが、すべての人にとって活躍できる場所とは考えていません。
「じゃあ、Readyforで活躍できる人はどんな人なのか?」と考えたとき、それはビジョンに共感していて、「ここでだったら自分の力を生かして自分の叶えたい夢を絶対叶えられる」と信じられる人だと思っています。
そんな仲間が集まることで、会社の価値や目指しているビジョンに向うスピードが上がるのではないでしょうか。
まとめると、「メンバーそれぞれの強みを理解して、その強みが発揮されるような環境をつくること」「ビジョンを掲げて、ビジョンに共感するメンバーを集めること」「お互いにコミュニケーションやチームビルディングをしっかりとして、信頼をしあう会社を運営すること」の3つを私はとても大切にしています。
「一緒に働く」には限界がある

岩本 僕の場合は、メンバーの強みとかは関係なく、とりあえず一緒にやってみようということでスタートしました。
もちろん、自分のお茶に対する熱意を1人1人に伝えて、その上で入っていただいていますが、一緒にメンバーがやる理由がビジョンというよりは僕個人に紐づいているので、その先のゴールを全員で共有できていない状況です。
米良 起業家って人に熱を伝えるのがすごく上手だと思うんですね。なので、「事業にはそこまで興味はないけど、この人と働きたい」というのは大切な要素です。
一方で、起業家が1対1で一緒に仕事できる人数ってやっぱり決まっていて。
私も全員を見たいと思っていましたが、しっかり見れていたのは20人、30人ぐらいですし、増やすにしても限界があるなと思っています。そんなときに会社と社員を結び付けるものが、「どこに向かいたいか」というビジョンではないでしょうか。
もちろん私と一緒に働きたいと言ってくれるのは嬉しいですが、その期待に応えられない可能性がある以上、会社全体が同じ夢に向かって走る組織をどうつくるかが重要です。
自己開示がサービスを成長させる

岩本 もう少し実務的な部分ですが、合宿をする際はどこまで参加者は自己開示をしていますか?
米良 自己開示は、かなり細かくやっていっているほうだと思います。
COOが自己開示のメソッドを考えるのが好きで、いろいろなツールを持ってくるので、それこそ自己開示系の時間だけで8時間ぐらいやっています。(笑)
しかも、うちの会社は社外取締役も合宿に来てもらって、全員で自己開示をするのですが、強みを生かすためにも、弱みも含めてお互いを理解するのは大切だと思います。
コミュニケーションは本当に難しいと思っていて、私みたいな起業家にとっては「昨日決めたことを今日やる」のが最高に心地がいいですが、人によっては「曖昧なままタスクを渡されてやらされる」ことが辛いこともあります。
されて辛いこと、嬉しいことをお互いに理解し合うということは大切だなと思っているので、100人ぐらいのスタートアップになるとみんなやっていると思いますが、執行役員の合宿やコミュニケーション研修を全員でやったりしています。
岩本抽象的にタスクを振るのが好きな人と嫌いな人がいたとき、その方々の間にタスクを細分化できる人を入れて、障壁を解決するということですか?
米良 そういったようにチーム編成を変える場合もあります。
あとは、マネージャーがしっかり入ることが大事だと思います。

プロフェッショナリティーが強い人が必ずしもマネージャーに向いているわけでも、マネージャーが必ずしもプロフェッショナリティーが高いわけでもなく、お互いに役割がそもそも違います。
マネージャーは、メンバー1人1人が価値を出せる環境を作ったり、コミュニケーションを設計するのが役割だと思っているので、そういう人にタスクの細分化を任せるのは1つの手だと思います。
私はタスクを細かくして渡すのは得意じゃないので、マネジメントを学んで、マネージャーになろうと思ったこともありましたが、結局あまり向かないと思って辞めました。(笑)
それからは私ができることは、マネジメントができる人を採用したり、その方が活躍できる状況をつくることだと考えてそちらに注力しています。
岩本 マネージャーとリーダーを正確に判断し、それを当事者にきちんと伝えるのは難しいと思うのですが、そこはどのようにされていますか?

米良 マネージャーという職務に向いている人と、現場でエースプレーヤーとして活躍する人は必ずいます。
この2つはどちらが偉いわけではなく、サービスが成長するためにはどちらも大事な役割だと思います。
そういった前提を共有した上で、マネージャーとプレイヤーのどちらのルートが、その人にとって一番価値を発揮できる道なのかを本人の強みや性格、実際のパフォーマンスなどをみながら一緒に考えていくようにしていますね。
岩本 やはり自己開示による強みと弱みの共有が重要なんですね。
米良 まさにそうですね。会社が大きくなると、毎月新しいメンバーが入ってくるんですよね。でも普通に考えて、知らない人が隣に座るってけっこうストレスだし、いやなことじゃないですか。
なので、すぐにお互い相談し合える環境をどうやってつくるのか試行錯誤しています。
会社というコミュニティの仕組み化

米良 私はもともとCEO、つまりチーフエグゼクティブオフィサーですが、最近COOから、「チーフイベントオフィサー」と「チーフエンターテインメントオフィサー」と名付けられて。
社内の大きいイベントは私と幹事のメンバーでやったりしています。
人数が多くなればなるほど、みんなで交流する機会は少なくなるので、「みんながどんどん自己開示して、相談し合いながらサービスを成長させ、社会に還元する」ということを徹底的にやれるように日々実験しています。
いろいろ言っていますが、私自身分からないことが本当にたくさんあるので、毎日トライ&エラーしながらやっています。
岩本 たとえば、あまりしゃべるのが好きじゃないメンバーでも交流が生まれるようにマネジメントするのは難しいなと思います。
そういったところはどうしていますか?
米良 私たちが一生懸命そういった人を他の人とつなげるというよりは、場をつくってあげて、メンバーが自走して解決していく状況をどうつくるか、そしてできるだけ人に依存しない仕組みにすることが重要です。
そして、始めた仕組みや、始めたことを絶対やめずに続けるにはどういったオペレーションをつくるかを考えることが私たちの役割なのではないでしょうか。
私も細かく何でもやりたがってしまいますが、最近はどうやったら回るかを考えるように意識しています。
岩本 お話を聞いていて、冒頭に質問した地域のおじいちゃん、おばあちゃんとのつながり方や、村社会との関わり方にも自己開示は通じると思いました。
組織論もコミュニティ論も結論は同じなんですね。
米良 全くその通りだと思います。
会社も1つのコミュニティでしかないので、それが地域になってもその地域の方々も一緒にビジョンを掲げて、「みんなで一緒にやっていこうよ」と、自分をさらけ出して巻き込んでいくことが大切かなと思います。
岩本 とても考えが整理されました。
ありがとうございました。
米良 私自身も経営者としてまだまだ未熟ですが、いろいろな人に失敗談も含めてたくさん経験を伝えて、ベンチャーの人たちがいい形で産業をつくっていけるように、頑張っていきたいと思います。