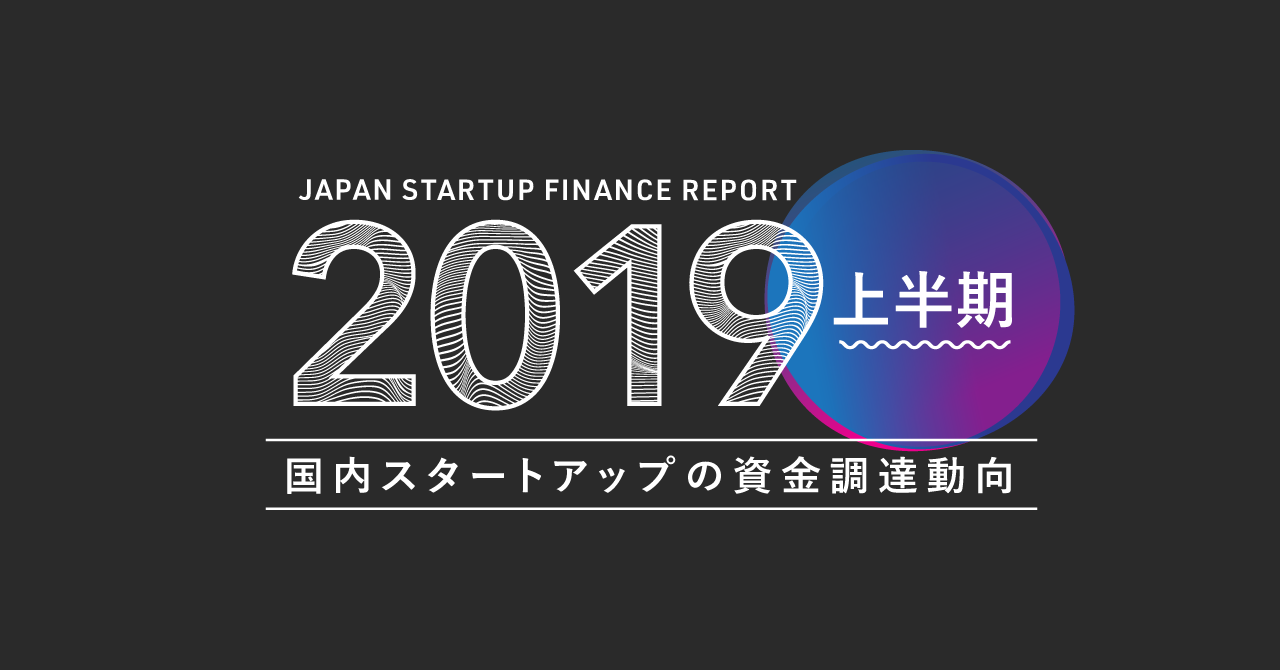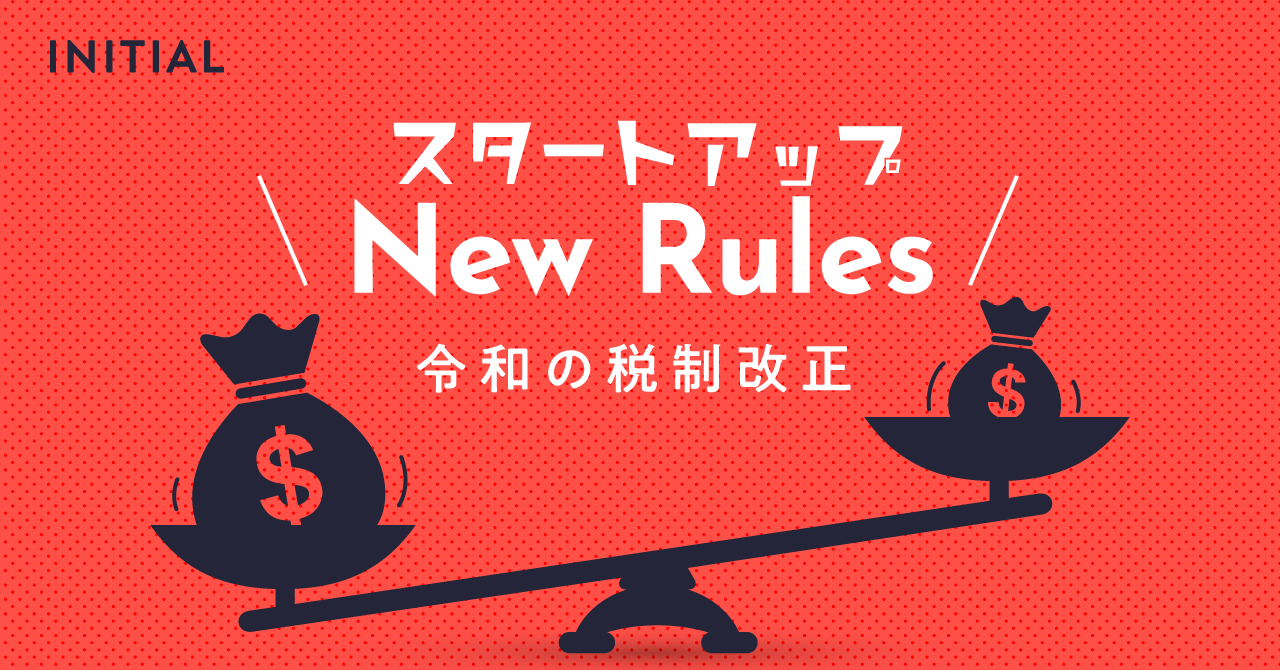事業法人からスタートアップへ、リスクマネーの供給が増えているー。
その流れを牽引しているのが、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)だ。金融や出版、化学メーカー、ITまで幅広い領域の企業が相次いで設立している。
アメリカのベンチャーキャピタルFresco Capital(フレスコキャピタル)のゼネラルパートナー 鈴木絵里子氏は、世界でCVCが急増している理由を『大企業はうまく「外部」と繋がる仕組みとしてCVCに期待を寄せている』と分析する。
しかし、CVCは投資経験が浅い事業法人が主体となって運営されていることから、運営方法や投資基準、組織のあり方などに課題を抱えていることが少なくないという。
今回は世界で60社以上のスタートアップに投資を行い、国内外のCVCをみてきた鈴木氏に、CVC成功に求められる「5つのポイント」について寄稿してもらった。
CVCが世界的に増加した背景
2011年以降、世界的にスタートアップ投資額が伸びている中、事業法人によるベンチャー投資、特にコーポレートベンチャーキャピタル(以下、CVC)によるスタートアップ投資額は史上最高を更新しています。
2018年には世界で新たに264社のCVCが設立。投資額は前年比47%増の6兆円以上、投資案件数は前年比32%増でした。アクティブなCVC投資家数も2012~2016年で2倍以上増えています(出所:CB Insights 「The 2018 Global Report」) 。

日本国内でも、2018年のスタートアップ投資全体の約49%、投資額として2000億円以上が事業法人による投資となっています。(出所:INITIAL「Japan Startup Finance 2018」)
CVC増加の背景は、世界中の企業が「オープン・イノベーション」の必要性を感じ、その突破口としてスタートアップに大きな期待を寄せているからではないでしょうか。
企業は本質的な「イノベーション」を起こすために、R&Dや新規事業創出プログラムなどの「内部」 の取り組み以上に「外部」(スタートアップなど)と繋がることが不可欠だと考えているのです。

CVCの発祥は1914年、米国DuPontによるGMへ出資
では、CVCはいつから始まったのでしょうか。米国CVCの歴史から振り返ってみましょう。
現在のCVCの形は1914年にまで遡ります。米国化学メーカーのDu Pont(デュポン)が当時スタートアップだった自動車メーカーのGeneral Motors(以下GM、ゼネラルモーターズ)へ出資したのが始まりです。
その後GMは急成長を果たし、自動車産業全体も拡大。Du Pontの合成革やプラスティック、ペンキなどの需要も大きく伸びました。
こうして、現在のCVCの基礎となる「財務リターンをあげると同時に、企業の戦略的意義も達成する」考え方が生まれました。
そのような歴史を振り返ると、CVCを成功させるためには以下の5つの視点が必要であることがわかります。

ポイント1:エコシステム思考
1点目は「エコシステム思考」。
自社だけでなく、スタートアップ全体のエコシステム構築を意識することが重要です。独立系VCやスタートアップと「相互扶助の関係」を築けるかが成功に大きく影響します。
米国半導体メーカーIntelのCVC「Intel Capital(インテルキャピタル)」を例にとり、説明しましょう。
同CVCは、個別スタートアップ企業の成功よりも、事業領域全体の振興を目的に投資を実行しています。
1999年にはマイクロプロセッサを使用する製品メーカー企業に特化した2.5億ドルのファンドを、2002年にはWi-Fiネットワーク規格のワイヤレステクノロジー関連企業向けに1.5億ドルのファンドを組成しました。
また、Salesforce傘下で世界有数のCVCである「Salesforce Ventures(セールスフォース・ベンチャーズ)」も、エコシステム思考がみられます。
同社の基幹事業である顧客関係管理(CRM)ツールに関連するスタートアップへ5億ドル以上投資するだけでなく、投資先に自社成長のノウハウや自社製品、チーム、顧客情報を提供しています。
逆に「スタートアップから技術やノウハウを収集し、自社で似たようなプロダクトを出せばいい」という考え方では、CVCの成功は望めないでしょう。
CVCがスタートアップと相互扶助の姿勢を見せなければ、昨今のように資本が充足している市況では、投資家・株主を選べる立場であるスタートアップはわざわざ投資を受けようとしないためです。
ポイント2:長期コミット
2点目、「長期的なコミット」も重要です。
CVCは通常、一定の金額や期間を決めてファンドを組成します。金額や期間が定まっているので、企業のバランスシート(貸借対照表)からの直接投資よりも、景況に影響されにくいのが特徴です。そのため、一般的には長期的な目標達成を目指しやすいはずです。
長期的な目標にコミットするには、明確な目標設定と体制が必要です。明確な目標や体制をもたずに、「他社がやっているから」「未来のために」のような抽象的な理由でCVCを立ち上げた企業は、景気に応じて投資活動からの撤退したり投資先のフォローが疎かになり、損失を出しやすい傾向があります。
上述のIntel Capitalは、最盛期にはIntelの総利益の3分の1を占める37億ドルもの利益を計上。しかし2001年頃にドットコムバブルが弾けた後は10四半期連続で損失を計上し、同社は苦境に陥りました。
その苦境の中でもIntel CapitalのCEO(当時) Leslie L. Vadászは投資を継続しました。結果的に1991年のCVC設立以来、同社は57カ国1500社以上のスタートアップに総額122億ドルを投資し、650社以上が上場または買収。継続投資の意思決定が功を奏し、優れた実績を残しています。
Intel Capitalでは、Intelの4人目の社員であり全ビジネスユニットのマネジメント経験もあったAvram Millerが副社長を務めました。CVCの経営陣が親会社の信頼を得ていたことで、長期的な目標にコミットできる体制になっていたのです。

(画像:Sundry Photography / Shutterstock.com)
一方で、総合エネルギー企業のExxonMobil(エクソンモービル)は、目的が不明瞭なままCVCを設立しパソコン領域のスタートアップに投資したため、数十億円近い損失を計上しました。
中途半端な目的で始め体制が不十分だったために、所属していた多数の投資家が「大企業」カルチャーに嫌気がさし辞めてしまった、GE Equityのような例もあります。
CVCの意義を「あったらいい」ではなく、企業のコア戦略と密接に関係させ「なくてはならない」ものにすることが鍵です。
ポイント3:ポートフォリオ戦略
3点目は「ポートフォリオ戦略」です。投資先1社1社の進捗ではなく、ポートフォリオ全体のパフォーマンス最大化を考えましょう。
CVC担当者は、短期的に成果が出やすい仕事とポートフォリオの成績を同様に考え、短期的な個社ごとのパフォーマンスを重視しがちです。
しかし、スタートアップの成果は数年~10年経たないと分かりませんし、失敗は必ずあります。また個社にフォーカスするあまり、ソーシングや関係性構築のために創業初期の企業に対する50万ドル程度の投資に時間を割くのも、限定的な人的リソースや投資対効率を考えると合理的ではありません。
CVCに求められているのは、投資先候補1社1社のリスク全てを最小限に抑えたり、優良企業をどこよりも早く見つけるスタンスではなく、ポートフォリオ全体のパフォーマンス最大化を考え、リスクを試算したうえで適切に投資するスキルです。
純粋な独立系VCでは、2割の投資案件がリターンの8割を生み出す「パレートの法則」が当てはまると言われています。CVCの場合は財務リターンだけにこだわらず、事業シナジーや新規ビジネス創出の観点も含めて、2割の大きな成果を目指す体制をつくるべきではないでしょうか。
ポイント4:バリュエーションへの理解と財務リターンへの注視
4点目はバリュエーションや財務リターンを妥協しないこと。
財務リターンの最大化が目的ではなくとも、スタートアップはエグジットまで調達をし続ける宿命にある中、随時適切なバリュエーションでの投資ができていないと、次期調達ラウンドでスタートアップが苦戦し、結局は事業拡大できなくなります。
また、各社によってリスクの計算方法や許容リスク量に関するポリシーは異なりますが、妥協をすると損害を被る危険性は少なくありません。
例えば医療系スタートアップの場合、「人の健康に影響を及ぼす」事業のため、リスクが大きいです。それにも関わらず、数値上の成長のみを重視して投資し、テクノロジーやビジネスの詐称行為が発覚し倒産する事例も起きており、注意が必要です。

(写真:Gorodenkoff / Shutterstock.com)
自社と同様の領域に投資する場合は、自社事業から得られる知見を積極的に活用すべきですし、異なる領域の場合は、適切な判断を下せる独立系VCや投資家に支援を求める必要があります。
特にCVCはリード(投資案件を主導する立場)を取らない場合が大半なため、バリュエーションに対して正確な判断を下せるVCや投資家を見つけることが必要です。
この体制を整備できれば、企業実態とはかけ離れたバリエーションやビジネスモデルの優位性を見抜くことができ、損害を受けるリスクを抑えることができます。
ポイント5:バリューアップへの執着
5点目は、投資先の企業価値向上(バリューアップ)への執着です。
独立系VCは金銭的なリターンのみを求められるため、スタートアップに対してハンズオン支援やノウハウの共有などを積極的に行っています。
一方CVCでは、企業側の制約が運営するうえで障壁となることがあります。例えば、決裁権限がない、担当者の人事異動、担当者と事業部の連携不足など組織形態面の制約が挙げられます。
また報酬面もCVCは成功報酬型のことが少なく、あまりリスクを取るインセンティブがありません。
米・印刷機器大手Xerox(ゼロックス)が1988年に設立したCVC「XTV(ゼロックス・テクノロジー・ベンチャーズ)」の例が、CVCの難しさをよく示しています。
同CVCの組織体制は、独立系VCと類似していました。例えば、投資担当者に200万ドルまでの投資権限を与え、よりリスクを取れるように報酬体系も成功報酬型を採用しました。
その結果、投資リターンは設立後8年間で2.2億ドルの利益と大成功を収めます。しかし、最終的には高額な報酬への批判などが高まり、1996年にCVCは廃止となりました。
企業側の独自制約に屈せず、組織の整備まできちんと行ったうえで投資先の成長にコミットできるかがCVCの成功に大きく影響すると言えます。
「エコシステム思考、長期コミット、ポートフォリオ思考、バリュエーションの見極め、企業価値向上に貢献」—これら5点を意識して運営できるCVCが、今後求められていくのではないでしょうか。

寄稿者プロフィール:鈴木絵里子(すずき・えりこ)/ Fresco Capitalゼネラルパートナー。4歳からアメリカ、カナダ、中東など海外で暮らす。カナダ・マギル大学卒業。モルガン・スタンレー、UBS証券で投資銀行業務、COACHで財務企画に従事。2015年よりアメリカ・ドローンベンチャーの日本立ち上げに携わる。2016年より社会的投資を行うミスルトウ投資ディレクターに就任。
(寄稿:鈴木絵里子、編集:町田大地、藤野理沙、デザイン:廣田奈緒美)