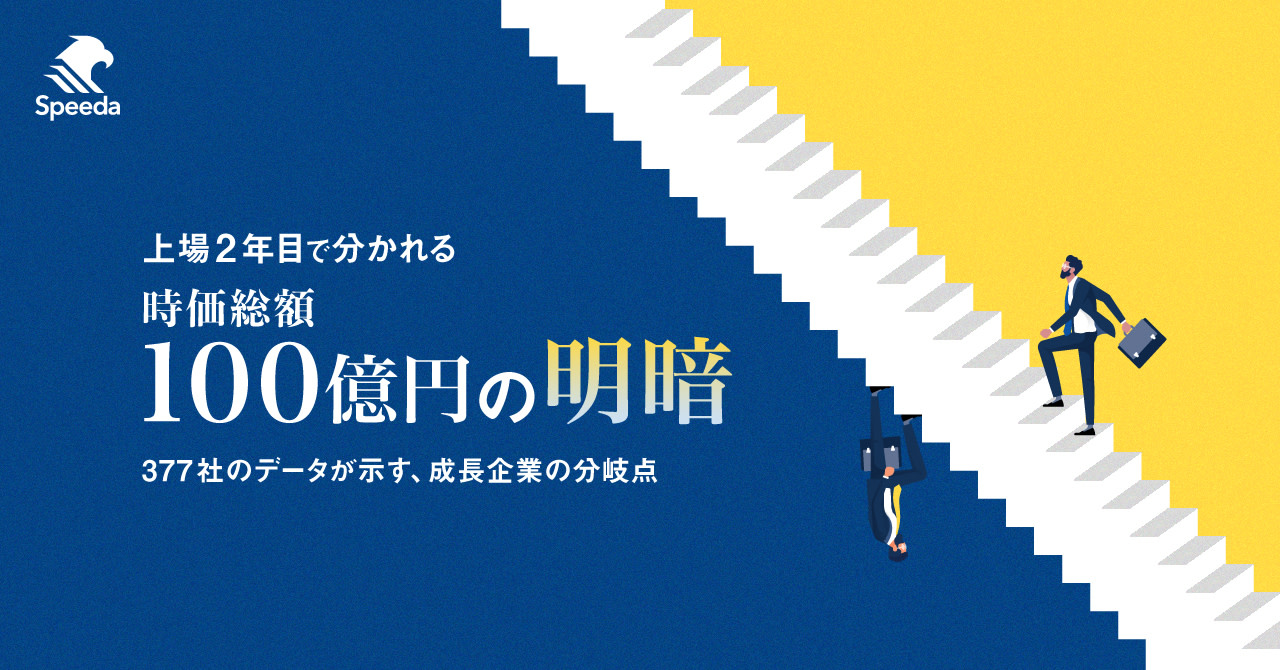東京証券取引所はグロース市場の上場維持基準を、現行の「上場10年経過後に時価総額40億円以上」から、2030年3月以降は「上場5年経過後に時価総額100億円以上」へと見直す方針を示した。成長企業向け市場としての信頼性と機能を確保するための措置であり、市場全体の質を高める動きが進んでいる。
こうした背景を踏まえ、Speedaでは過去に時価総額100億円未満で上場した377社を対象に、上場後5年以内に100億円へ到達した企業と、到達しなかった企業を、財務指標や株価推移など多角的なデータから比較分析した。その結果を基に、グロース市場で求められる成長水準をより具体的に示すことを試みた。
※本記事は、Speeda調査レポート『時価総額100億円超え企業の実態調査からみるスタートアップへの示唆』の一部を抜粋したものです。全データ、詳細分析、有識者インタビューを含む完全版は有償で提供しています。
👉「時価総額100億円の壁を超えたスタートアップの実態」をお選びください
なぜグロース市場の上場維持基準は引き上げられるのか
東証グロース市場の上場維持基準が、上場5年以内に時価総額100億円以上へと引き上げられる方針が示され、2025年のスタートアップ業界では大きな関心を集めるテーマとなっている。
現在の基準は「上場10年経過後に時価総額40億円以上」だが、2030年以降は「上場5年経過後に時価総額100億円以上」へと見直される予定だ。
市場再編の経緯と課題
東京証券取引所(以下、東証)は2022年4月、旧市場区分(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)をプライム・スタンダード・グロースの3市場へ再編した。
市場再編後、プライムとスタンダード市場は指数ベースで比較的底堅い動きを維持している。一方、グロース市場は海外グロース株の調整も影響し、投資家のリスク選好が戻らない状況が続いた。さらに、多くの企業で上場後に成長が鈍化し、「成長企業向け市場」として十分に機能していない点も課題とされてきた。
こうした状況から、東証はグロース市場の信頼性と魅力を高める必要があると判断し、上場維持基準を見直して「高い成長を実現できる企業が集う市場」へと再構築する方針を示した。
ただし、新基準は即時適用ではない。規則改正は2025年12月中を予定しており、実際の適用は2030年3月1日以降、最初に到来する事業年度の期末からとなる。

東京証券取引所:2025年9月26日公表資料より
また、基準未達の企業でも、基準に適合するための計画を開示すれば、その計画期間中は例外的に上場を継続できる猶予措置が設けられている。
さらに、今回の見直しに伴い、スタンダード市場への移行を検討する企業が増える可能性もある。現行の市場区分変更では年1億円以上の利益が必要だが、これを上場維持基準と揃えることで、スタンダード市場への移行をしやすくする制度の整備が進められている。
過去20年のデータで読み解く「時価総額100億円未満でIPOした企業の成長」
今回の基準見直しは、成長企業としてどのような実績を示すべきかを、これまで以上に明確に問うものとなる。では、過去の上場企業は実際にどのような成長軌跡をたどってきたのか。
グロース市場の前身であるマザーズ市場が開設された1999年から2020年までの間に、公募時価総額100億円未満で上場した377社を対象に分析を行った。
377社のうち、上場5年後に時価総額100億円を超えた企業は118社で全体の31%にとどまった。多くの企業がIPO後に十分な企業価値の拡大につなげられていない現状が浮き彫りとなった。

Speeda調査レポート『時価総額100億円超え企業の実態調査からみるスタートアップへの示唆』より
時価総額の推移をみると、上場後2年を境に成長軌道が大きく分岐していた。5年後に100億円へ到達した企業は一貫して企業価値を伸ばし続けたのに対し、未達企業は2年目以降に成長が鈍化し、停滞から縮小へと向かう傾向が見られた。

Speeda調査レポート『時価総額100億円超え企業の実態調査からみるスタートアップへの示唆』より
この分岐がどこから生じるのかを明らかにするため、「5年後に100億円へ到達した企業」と「未達企業」の2群に分け、上場時の特徴と上場後の実績を比較した。
上場時のデータを統計的に比較したところ、「初値時価総額」「売上高成長率」「従業員数」といった成長性や規模感を示す指標では、時価総額100億円以上の企業群と未満の企業群の間に明確な差は見られなかった。
より重要だったのは、上場後にどれだけ事業を成長させられたかという点であった。
特に注目すべきなのは、会社予想の売上高と営業利益の達成率である。100億円に到達した企業の多くは、売上高・営業利益ともに会社予想を継続的に達成していた。
一方、未達企業は上場後初年度から達成率が低く、売上高38.6%、営業利益45.5%にとどまった。その後も未達が積み重なり、5年後に予想を達成していた企業は売上高19.7%、営業利益23.3%まで低下していた。
決算発表直後の株価変動率をみても、100億円到達企業ではほぼ横ばいだったのに対し、未達企業では平均1%超の下落が続いており、市場は計画未達に対して厳しく反応していた。
このことから、企業価値の分岐を左右していたのは、「事業計画を実行し、計画通りに成長できたかどうか」にあったと言える。
日本ベンチャーキャピタル協会会長・UTEC代表の郷治友孝氏は、「業績予想と実績がどの程度一致しているかは、企業の計画性や実行力を見極めるうえで非常に重要だ。最終的には、成長を数字でどれだけ示せているかがすべてを左右するため、計画を確実に実行し、実績を積み重ねられるかが問われている」と指摘する。
この「計画通りに成長し続ける力」が時価総額の伸びに直結することを示す代表的な成功例が、2015年12月に上場したPR TIMESである。

PR TIMESサイトイメージ/同社プレスキットより
同社の上場時点での時価総額は、公募価格ベースで41億円、初値ベースで64億円と、いずれも100億円未達企業と大きな差はなかった。業績も上場年の通期で売上高10.8億円、営業利益1.8億円にとどまり、むしろ100億円未達企業の中央値(売上高27億円、営業利益3億円)を下回る規模だった。
それでも同社は、上場後5年間にわたり、業績予想レンジ内で売上高・営業利益の双方を着実に達成してきた。特に売上高は、創業から現在(2025年2月期)まで18期連続で増収を続けており、持続的な成長力を裏付けている。こうした積み重ねにより、上場から5年後の2021年4月には時価総額が434億円にまで到達した。
代表の山口拓己氏はこの成長の背景について、「短期的には市場の変動に左右される株価も長期的には実績と信頼に収れんすると考え、株価に一喜一憂せず事業の成果で価値を高めることに集中してきた」と語る。
上場後は「5年で2倍・3倍、あるいはそれ以上」という大きな成長目標を掲げ、計画ではなく「目標」として野心的な姿を明確に示してきた。
上場5年で時価総額100億円到達に向けて求められる業績
上場後に時価総額100億円へ到達した企業のデータからは、100億円到達に必要となる業績水準が具体的に見えてくる。

Speeda調査レポート『時価総額100億円超え企業の実態調査からみるスタートアップへの示唆』より
成長率では、売上高・営業損益・純損益のいずれも年平均で30%前後の成長を5年間にわたり継続する必要がある。具体的には、売上高26%、営業損益32%、純損益29%程度が1つの目安となる。
規模面では、上場から5年以内に平均して売上高64億円、営業損益5.5億円、純損益3.5億円を実現していた。黒字を確保しつつ継続的に成長できるかどうかが、市場からの評価を左右することがわかった。
こうした状況について、ユーグレナのCEOを務めていたUntroD Capital Japanの永田暁彦氏は、「増資でもいいし、株式交換によるM&Aでもいい。とにかく、上場後1〜2年の間にコーポレートアクションを伴う成長戦略をやり切ることが大切だ」と指摘する。早期に成長の選択肢を広げ、規模と収益の両立に向けた布石を打てるかどうかが、その後の成長軌道を左右するという。
上場後に差がつく「未上場時の仕込み」
上場後に持続的に企業価値を高めていくためには、IPOの時点から数年間でどれだけ成長ストーリーを示せるかが重要になる。今回の分析では、上場2年目以降に時価総額の明暗がはっきりと分かれることが確認された。
「未上場時から上場後を見据えた成長戦略を具体化し、実行フェーズに入っておく必要がある。ビジョナルやメドレーは上場前に大規模な先行投資を行い、上場後にその成果を回収する体制を整えていた代表例だ。N-1期までに大きな成長投資を実行することが、1つの選択肢になる」(グロース・キャピタル嶺井政人氏)。
上場企業が直面するのは、四半期ごとに進捗が可視化され、日々市場から評価を受け続ける環境である。その中で持続的に事業を成長させるには、中長期の成長戦略と経営体制を未上場期から整えておくことが欠かせない。
アイスタイルでは、2017〜2020年度に策定した中期経営計画が環境変化に十分対応できず、最終年度となる2019年度には「売上高・営業利益ともに大きく乖離」する結果となった。計画は1年先延ばしを余儀なくされ、株価下落にもつながった。
同社CFOの菅原敬氏は、「セグメント別の業績や人員計画まで詳細に定めたため、事業環境が変わっても当初の計画に沿った戦略を進めざるを得なかった。投資家が求めていたのは、細かい数字の公開ではなく、数年後にどんな会社になりたいのかというビジョンと、その道筋を裏付ける指標を示すことだった」と振り返る。
こうした反省を踏まえ、2024年8月に公開した中期事業方針では、精緻な計画ではなく、実現したい数字を「4〜5カ年のレンジ」で示す方針へと転換した。
上場後の成長には、経営管理や計画策定だけでなく、ガバナンスの質も大きく影響する。
日本ベンチャーキャピタル協会会長でありジェネシア・ベンチャーズ代表の田島聡一氏は、「ガバナンスは企業の動きを縛るための“守り”ではなく、正しい意思決定を迅速に後押しする“攻めのガバナンス”であるべきだ。特に、社外取締役は人数ではなく、企業フェーズに合わせた経験・視点をもつ人材を早期に迎え入れる必要がある」と指摘する。
こうしたガバナンスや意思決定体制が未上場期から整っている企業は、上場後に日々の株価変動や四半期ごとの評価にさらされても、事業成長の軸がぶれにくい。求められるのは、上場前後の数年間をどう設計し、一貫した成長ストーリーとして市場に提示できるかである。
その積み重ねこそが、上場2年目に明暗が分かれる「100億円への分岐点」をつくり出していた。
(執筆:平川凌、デザイン:川﨑菜々美)
※本記事は、『時価総額100億円超え企業の実態調査からみるスタートアップへの示唆』の一部を抜粋したサマリー版です。全データ、詳細分析、有識者インタビューを含む完全版は有償で提供しています。
👉「時価総額100億円の壁を超えたスタートアップの実態」をお選びください
レポートは「EXPERT Growth Hack Report」シリーズの1つとして提供しており、他レポートとのセット購入にも対応しています。