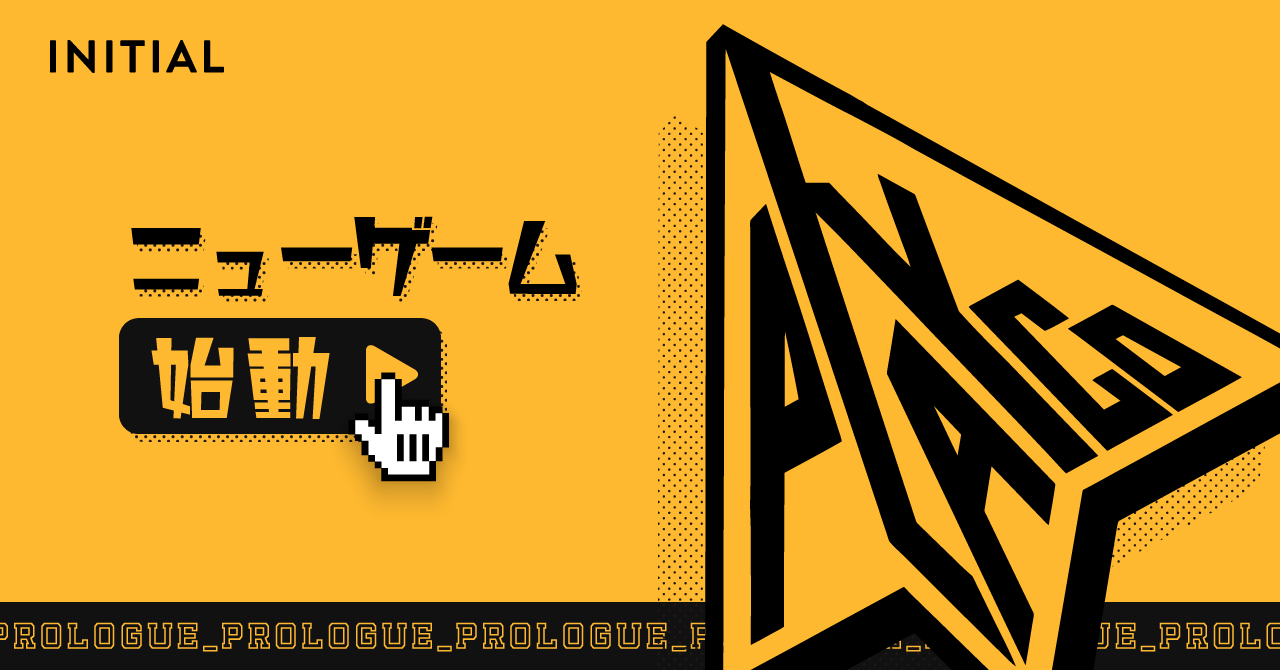コロナ禍で世界の情勢が大きく変化するいま、過去最高の業績を更新し続ける絶好調の業界がある。任天堂に代表されるゲーム業界だ。
そのゲーム業界で、FacebookなどSNS上で遊べる「インスタントゲーム市場」に注目が集まっている。誰でも簡単に遊べて、世界中の30億人以上がプレイヤーの対象だ。
しかし、新たな市場であるため、インスタントゲームのビジネスモデルや成長性は謎に包まれている。
そこでINITIALでは世界で初めてインスタントゲーム開発に特化したユニコーン企業、Playco共同創業者シニア・ヴァイス・プレジデントの大塚剛司氏、Playcoに投資したEast Venturesパートナーの衛藤バタラ氏の両名に独占取材を実施。
なぜ今、インスタントゲーム市場が熱いのか。モバイルゲームやソーシャルゲームと何が違い、今後どの程度の成長が見込まれるのか。インスタントゲームにまつわる5つの疑問を解説していく。


インスタントゲームとは?つながり重視、手軽でスキマ時間で遊べる
まず、インスタントゲームの概要について解説する。
インスタントゲームとは、スマホなどデバイス上でのアプリダウンロードが不要で、世界中の誰とでもすぐにプレイできるゲームを指す。
従来のモバイルゲームはアプリダウンロードが必要で、時間をかけて遊ぶことが多いのに対し、インスタントゲームはFacebook、LINEなどメッセンジャーアプリ内でプレイできる。
East Venturesの衛藤氏は、インスタントゲームについて「ソーシャルグラフ(ユーザー同士のつながり、ネットワーク)を活用していることが一番の特徴です。ゲームよりもコミュニケーションツールに近く、位置付けとしてはコミュニケーションツールとモバイルゲームの中間にあるイメージです」と語る。
ソーシャルグラフを活用することから、ゲーム内容よりも「誰とやるか」が重視され、プレイ相手は友人中心でシンプルなゲーム仕様になっているケースが多い。

またRPGなど長期間のプレイを前提とした複雑なゲームに比べ、インスタントゲームは5分程度のスキマ時間でプレイできる。
インスタントゲームはSNS上で手軽に遊べるため、ソーシャルグラフによるネットワーク効果でプレイヤー数が伸びやすい。その反面、プレイヤーを定着させることがモバイルゲームに比べて難しい傾向がある。
またインスタントゲームはHTML5と呼ばれる技術をベースにしており、RPGのように複雑な表現が要されるゲームを作ることは難しい。しかし技術の進歩により、数年前に比べて複雑な表現はできるようになっている。
Playcoは2020年12月14日にFacebook上で遊べる2つのインスタントゲームをリリースした。そのうちの1つはPlaycoが独自に開発した「Cat Life!」で、プレイヤーがルーレットを回して賞品を獲得しながら、様々な種類の猫を集めることができるゲームだ。

Playcoが12月にリリースを発表したインスタントゲーム「CAT Life!」(出所:Playco メディアキット)
ビジネスモデルと成功のカギは?
次に、インスタントゲームのビジネスモデルを解説する。
モバイルゲームと同様に、インスタントゲームの収益モデルは広告、課金の2つの仕組みが中心だ。前者の広告モデルではプレイヤーが無料でゲームができる代わりに広告が表示され、プレイヤー数に応じて広告出稿会社からゲーム企業に料金が支払われる。後者の課金モデルではプレイヤーによるプレイ中のアイテム課金がゲーム企業の収益となる。

上記の収益構造は、モバイルゲームとインスタントゲームの違いによって生まれるものではなく、ゲームの種類によって異なる。たとえば、クオリティの高いRPGゲームではゲームに没頭する少数のコアプレイヤーがアイテム課金の中心だ。対して、誰でも簡単に遊べるハイパーカジュアルゲームではプレイヤー獲得単価を低く抑え、多くのプレイヤーを集めて広告モデルで資金を回収していく。
課金・広告モデルの比率を開示している企業は少ないが、モバイルゲーム企業のZyngaの場合、課金:広告が8:2の割合だ。インスタントゲームを開発するPlaycoの場合は、トップダウンで課金・広告モデルの比率は決めてないという。
インスタントゲーム企業・Playcoの大塚氏はその理由を、「ゲームによって収益モデルの特性も違いますし、多くの人が長く遊べるゲームを作れば、課金でも広告でも収益はついてくる。創業1年目のPlaycoでは、今は単価をあげることよりも面白いゲームをつくることにフォーカスしています」と語る。
逆にリスクは、「ヒットコンテンツとなるゲームを生み出せないリスク」(大塚氏)のほか、「プラットフォーム上でゲームを展開しているため、プラットフォームの仕様変更によるリスク。規模が拡大してもスピード感のある開発・リリースできる体制を維持できるかなど採用を含む執行リスク」(衛藤氏)があげられる。
プラットフォームの仕様変更に関して、Playco大塚氏は「プラットフォーム企業側もインスタントゲームに関しては手探りの状態です。どのように集客するのか、メッセージを送るタイミングやUIの仕様など、細かい部分も含めてゲーム開発企業と議論しています」と語る。
また事業のカギおよびリスクとなるヒットゲームの生み出し方について、大塚氏は「ゲームはエンタメビジネスです。エンタメ業界はコンテンツと技術の両輪で成り立っていて、ヒットコンテンツがないと技術も市場も成長せず、人も資金も集まりません。ヒットゲームを生み出す確率をあげるためにも、いかに素早く開発して仮説検証を繰り返せるかが大切です」と語る。
Playcoの創業者はインスタントゲームに用いられるHTML5の技術力を持つマイケル・カーター氏だが、Zyngaでヒットゲームを生み出し組織の急拡大に対応したジャスティン・ウォルドロン氏、DeNAで怪盗ロワイヤルを生み出した大塚氏など、プロダクト・コンテンツサイドに強いメンバーも共同創業者となっている。Playcoの経営体制はゲーム業界に必須なコンテンツ・技術の両方に強いメンバーを兼ね備えており、有利といえよう。

なぜ今なのか?インスタントゲーム台頭の背景
ソーシャルゲームが急速に勃興してブームが過ぎ去った2010年代。インスタントゲームとソーシャルゲームには、ソーシャルグラフの活用などの共通点がみられる。しかし、なぜ今2020年代に再びトレンドになっているのか。市場環境の変化の背景に迫る。
インスタントゲーム台頭の背景は3つある。
1つめは、SNSユーザー数の増加だ。
現在のFacebookユーザーは約30億人と2010年代と比較して3〜4倍の規模になっている。日本国内でもLINEのMAUは1000万人から8000万人まで成長した。スマホ保有ユーザーの増加を背景に、SNSユーザー数がこの10年間で爆発的に伸びている。
インスタントゲームはSNS上でプレイするため、SNSユーザー数の増加は対象プレイヤー数の拡大を意味する。2010年代にもFacebookでプレイできるZyngaなどのソーシャルゲームは存在していたが、単純にユーザー数だけでも潜在市場規模は数倍以上になっている。
2つめは、ソーシャルグラフの基盤が安定したことだ。
2010年代に一世を風靡したDeNA、GREEなどのゲームが下火になった理由のひとつは、リアルな人間関係のつながりを保有するFacebookにユーザーが移行したことだ。背景として、Facebookのグローバルに繋がる基盤を持った強み、実名を前提とした匿名性の排除、「いいね!」のパイオニアである点でSNSとして強かったことが挙げられるだろう。
結果、SNSを通じてゲーム企業が独自に保有していたソーシャルグラフの価値が下がってしまった。しかし、インスタントゲームでは淘汰を経て強固になったソーシャルグラフの価値を活用できる。なぜなら、インスタントゲームは他人ではなく友人同士でプレイできることに価値があり、リアルな人間関係・周りのネットワークが重要になるからだ。
Facebookを中心にソーシャルグラフが確立された一方で、SNSプラットフォームも多様化が進み競争が激化している。Facebookのほか、Instagram、SnapChat、iMessageなどメッセージ送信だけで多くのプラットフォームが混在し、プラットフォーム企業側もユーザーのエンゲージメント向上が課題になっている。
インスタントゲームがアクティブユーザーを増やす施策としてプラットフォーム企業側から捉えられ、双方win-winとなっていることも背景に挙げられる。特にPlaycoは特定のプラットフォームに依存することなく、LINEやSnapchatなど多くのプラットフォーム企業と提携している。
3つめは、プラットフォーム企業のルール整備が進んだことだ。
Facebookは2017年からインスタントゲームの展開を開始していたが、「当時はソーシャルメディアなのかゲームサービスなのか、企業におけるインスタントゲームの位置付けが明確でなかった」(衛藤氏)。
試行錯誤の結果、リリースから3年経って「ようやくFacebook側でもインスタントゲームの位置付けが整理されて、彼らが提供するAPIのルール化が進んだ」(衛藤氏)ことも背景にあるだろう。

市場の成長と市場規模はどれくらい?
では、今後インスタントゲーム市場はどれだけ成長するのだろうか。市場の成長性と市場規模について解説する。
世界のモバイルゲーム市場規模(2020年)は772億ドル(日本円で約8.1兆円相当、1ドル=105円換算。出所:New Zoo Global Market Report)となっている。
インスタントゲーム市場の考え方として、モバイルゲーム業界からシェアを取る形になるのか、それとも完全に新たな市場として定義するのか。
投資家の衛藤氏は、「インスタントゲームの対象プレイヤーは、普段ゲームをしないような人たちが中心です。ゲームの特性上プレイヤー層が異なるため、モバイルゲーム市場との取り合いは一部で、むしろソーシャルグラフとの関連性でギフティング(投げ銭)市場に近い」と語る。
一方ゲーム企業側の大塚氏は、「インスタントゲームを『スキマ時間に消費するデジタルコンテンツ』と捉えることができます。この見方にもとづくと、モバイルゲームよりもむしろ動画サービスがライバルになる」と語る。
市場の考え方について、モバイルゲームとは異なる業界を類似・競合として捉えていることがわかった。それでは、どの程度の成長が見込まれるのか。実現可能な市場規模(Total Addressable Market、TAM)の考え方について、再び二人に聞いた。
投資家の衛藤氏は「TAMはモバイルゲーム市場の一部と、潜在プレイヤー数と一人当たり売上高(APRU)の仮定を置けば計算できます。しかし、インスタントゲーム市場はまだ存在しない市場のため試算は難しく、モバイルゲーム市場の成長率を上回るかは分かりません。ただし、投資家としては今後伸びると確信できる新しい市場を独占できるかどうかが重要です」と語る。
大塚氏は、TAMの考え方についてこう語る。
「たとえば、インスタントゲーム業界全体で仮に5000億円市場を目指すとしましょう。Facebookユーザー約30億人中、3人に1人の10億人がプレイすると仮定したら、一人当たり年間平均売上高(ARPU)は500円で、1ヶ月に換算すると約40円です。課金率を5%と設定すると課金ユーザー数は5000万人、一人当たり年間課金額は10,000円、1ヶ月に換算すると800円程度なので、そこまで非現実的な数字ではないと考えています」
ソーシャルゲーム全盛期、当時のDeNA・GREEの売上は約1000億円前後だった。当時と比較してモバイルユーザー数やSNSユーザー数は7〜8倍になっていることからみても、中長期的にインスタントゲーム市場規模は数千億円は十分に狙える範囲であろう。
また、モバイルゲーム企業のZyngaの2020年売上高見込みは約2000億円(約19億ドル)で、時価総額は約1兆円(100億ドル)前後で推移している(2020年12月現在)。Playcoの評価額は約1000億円を超えているが、市場規模や類似企業の売上規模から逆算すると、割高ではなく妥当な水準であるといえよう。

市場の主要企業は?Playcoがリード
最後に、インスタントゲーム市場の企業について見てみよう。
Facebookや中国・テンセントのプラットフォーム上には多くのインスタントゲーム開発企業が存在する一方で、「ソーシャルグラフに注目しているゲーム会社は、現段階ではあまりいない」(Playco大塚氏)という。
そのため、現在の主要企業は世界で初めてインスタントゲームに特化したPlaycoだといえる。しかし大塚氏は「競合というよりも、一緒にインスタントゲーム市場を盛り上げるゲーム開発企業が増えてほしいです。市場が盛り上がる方がプレイヤーさんも選択肢が増えますし、逆にわれわれ1社だけでは心配になります」と語る。
投資家の衛藤氏は、まだ市場が存在していない段階でPlaycoへの投資を決断した。その理由として、インスタントゲーム市場に必要なHTML5技術のノウハウを保有している点、FacebookやLINEなどプラットフォーム企業と一緒に市場を共創している点、ソーシャルゲーム分野での成功体験のある経営チームの3点をあげている。
衛藤氏は今後について、「市場が伸びるにつれて競合も参入してくると思いますが、HTML5技術で10年近く事業を展開してきた技術的な参入障壁や、プラットフォーム企業と強固な関係を築いていることから、Playcoの優位性は保持されるでしょう」と期待を込めて語っている。

2020年9月にPlaycoが約100億円(1億ドル)調達をしたほか、2020年11月には元DeNA China CEOの顧氏が立ち上げたゲーム企業「5X Games」が設立と同時に15億円の資金調達を発表するなど、ゲーム業界はいま資金調達面でも注目が集まっている。
世界で初めてインスタントゲームに特化したPlaycoが今後も業界をリードして市場を開拓しながら、他のゲーム開発企業も参入してくるであろう。
「われわれのミッションはプレイを通じて世界中の人々をつなげること。あくまでミッション到達のためのゲームや技術です」と語るPlayco大塚氏。
今後Playco含むインスタントゲーム市場に参入する企業は、ソーシャルゲーム業界の盛衰から学び、プレイヤーに愛されるゲームを生み出して持続的に成長していけるかが鍵になりそうだ。
(取材・文:藤野理沙、編集:中村香央里、デザイン:石丸恵理)